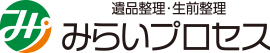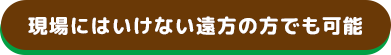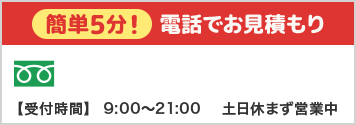50代の終活で断捨離が必要な3つの理由~やってはいけないパターンも解説~
「終活」という言葉が登場した頃には、「60代や70代でやるもの」というイメージを多くの人が持っていました。しかし、今は「50代から始める」という方も増えています。
これは「終活をしていなかった親御さんの死を目の当たりにした」「それを見て、自分は早めに終活をすると決意した」という理由も多いでしょう。以前からそのような親御さんは多く見えたのですが、「終活」という言葉がブームになった後では、そうした親御さんを見た後に生まれる意識が変わったということです。
そのような理由で「50代の終活」が活発になりつつありますが、中でも特に重要なアクションの1つが「断捨離」です。この記事では50代の終活での断捨離について解説していきます。「50代から終活を始めたいが、具体的にどう進めるべきかわからない」という方には、特に参考にしていただけるでしょう。

- 50代の終活で断捨離が重要な3つの理由
- 精神面…人生で大事なものを絞る必要がある
- 能力面…体が自由に動くうちにする方がいい
- 健康面…突然死のリスクも上昇する
- 50代は断捨離しない方がいい?批判派の3つの主張
- 家族とトラブルになるから
- 年金生活になると新しいものを買えないから
- 今までやらなくても50年間平気だったから
- 妻がしてはいけない断捨離(捨てるとトラブルになる物)
- 置いてあるだけで、夫自身も全然使っていない物
- 夫の思い出の品だが、汚くて臭い物
- 物自体は普通だが「その中に何か入っている」物
- 主婦がやってはいけない断捨離とは?
- 理想の生活を過度に追求する
- 経済力がない状態で、使える物を捨ててしまう
- 「子供の物は勝手に捨てていい」と考える
- 50代でシンプルライフを送るために整理すべき場所
- キッチン…吊戸棚にある物は捨ててかまわない
- 和室…来客用布団は捨ててレンタルにする
- 風呂場…物が少ないので判断しやすい
- 終活・断捨離を含めた生前整理はプロにご相談を!
- まとめ
50代の終活で断捨離が重要な3つの理由

50代の方が終活を始めるときに、断捨離を重視するべき理由は、下の3つです。
- 精神面…人生で大事なものを絞る必要がある
- 能力面…体が自由に動くうちにする方がいい
- 健康面…突然死のリスクも上昇する
ここではそれぞれの理由について詳しく解説していきます。
精神面…人生で大事なものを絞る必要がある
断捨離とは物を捨てることです。そして、物を捨てることは「何かの価値観を捨てる」ことでもあります。
野球のグローブを捨てるなら「野球を辞める」ということであり、ギターを捨てる(売る)なら「音楽を辞める」ということです。もちろん「また買えば再開できる」ともいえます。しかし「今より難しくなる」のは確かです。
つまり、断捨離をするには「人生で大事なもの」を絞る必要があります。そして、50代ではある程度、これが絞られている必要があります。
50代から先の選択肢は限られている
言うまでもないことですが、50代から先の人生は、選択肢が限られています。たとえば70代で演歌歌手としてデビューした方などもいますが、こうした方は「若い頃からある程度うまかった」ものです。老後にゼロから始めたわけではありません。
つまり、50代から新しい道を志すにしても、それは「若い頃に積み上げたものの延長線上」になくてはいけません。「いけない」というと語弊がありますが、これまで積み上げたものの上で勝負する方が、有利なのは確かでしょう。
仕事にしてもプライベートにしても、50代になると「今後の人生で何をやるのか」「何をやらないのか」を明確にする必要があります。その具体的な行動の1つとして「断捨離」が重要になるのです。

能力面…体が自由に動くうちにする方がいい

こちらは物理的かつ肉体的な理由ですが、終活にはそれなりの体力が要ります。物を処分するための力仕事もあれば、あらゆる手続きに走り回ることもあります。
このようなことは、60代になると50代より難しくなるものです。まったく同じ仕事でも、50代なら簡単にできたことが、60代だと難しくなります。
どうせやるなら、楽なうちにやる方がいい
終活というのもは、最終的にしなければならないもの。その度合いは人によりますが、誰でも「何かはしなければいけない」のです。
そして、どうせその「何か」をするのであれば、まだ若くて楽にできるうちに済ませてしまう方がいい、といえるでしょう。この点でも、特に体力が必要になる断捨離は、50代のうちから始める方がいいのです。
健康面…突然死のリスクも上昇する

「縁起でもない」といわれるかもしれませんが、50代は40代よりも、突然死のリスクが上がります。また、突然死だけでなくガンなどの重い病気にかかるリスクも高くなるものです。
突然死してしまえば、当然遺族は困ります。そのとき、親の自分が何も終活をしていなかった理由が「縁起でもないから」という根拠のないものだったら、特に子供たちに対して申し訳ないでしょう。
「縁起でもない」という人ほどリスクがある
失礼と感じずに読んでいただきたいのですが、これは社会人の方であれば多くの方が納得してくださるのではないかと思います。生死に限らず、悪いケースを「縁起でもない」といって考えない人ほど、そのようなケースに遭遇しやすいのです。
逆に、そうした「縁起でもないこと」を逃げずに受け止め、的確なシミュレーションと準備をする人ほど、そのようなケースに遭遇せずに済みます。
東日本大震災で唯一、死傷者・行方不明者がゼロだった町
東日本大震災で、津波が直撃した岩手県沿岸にありながら、唯一死傷者も行方不明者もゼロだった町があります。「洋野町」という町で、NHK朝ドラ「あまちゃん」の舞台にもなった場所です。
「海女のストーリーの舞台だから、全員泳ぎが得意だったのか」などと思うかもしれませんが、もっとシリアスな理由です。実は、この町は津波リスクが極めて高い場所にありながら防潮堤や保安林など、あらゆる防災設備がなかったのです。
過去の災害から「このエリアは危険」ということがよくわかっていました。実際、下の画像のように、他の自治体と同様の被害を受けています。
 画像引用元:東日本大震災 死傷者ゼロだった「あまちゃん」の町の奇跡(フォーブス・ジャパン)
画像引用元:東日本大震災 死傷者ゼロだった「あまちゃん」の町の奇跡(フォーブス・ジャパン)
それでも一切の人的被害がなかったのは「住民全員に危機感があった」ためです。「危険な場所なのに丸腰」ということを、町の職員も住民もよく意識しており、普通の自治体ならおそろかにされる防災教育が、真剣に行われていました。
つまり「縁起でもないこと」をどの自治体よりも考えていたから、それが起きなかったのです。縁起でもないことは「むしろ考えるべきである」ことが、この事例からもよくわかるでしょう。
50代は断捨離しない方がいい?批判派の3つの主張

家族とトラブルになるから
まず、50代に限らずすべての年代で主張されるのが、この理由です。「自分の物を捨てるだけ」ならいいのですが、家中を綺麗にしようと思うと、どうしても家族の物をある程度捨てる必要が出てきます。
勝手に捨てないのはもちろんですが「捨てよう」と提案するだけでもトラブルになることがあります。50代になると価値観やライフスタイルも固定されており、配偶者にそうした提案をしても拒否されることが少なくありません。
このような理由から「50代では断捨離をしない方がいい」と主張する人も多いのです。
年金生活になると新しいものを買えないから
特に「貯金があまりない家庭」で多く見られる主張がこれです。確かに今の年金制度では、これから支給額がさらに減っていき、支給開始年齢も引き上げられるでしょう。
そうなると「定年退職以後に新しいものを買うのが難しくなる」といえます。「捨てたら二度と買えないから、保存しておくべき」という考え方は一理あるでしょう。
ただし、これは「経済的な不安がある家庭」の場合です。そのような不安がないなら、健康管理も含めたあらゆる仕事をスムーズにできる環境を整えるために、断捨離は適度に実行すべきといえます。
今までやらなくても50年間平気だったから

「50年以上問題なくやってきたのだから、今のままでいい」という考え方です。確かに、これも一理あるでしょう。ただ「これでいい」と周囲も思っているかはわかりません。
- 平均的な同世代と比べて健康か
- 同じく平均的な家庭と比べて部屋は綺麗か
このような視点で「客観的に見る」必要があるでしょう。もちろん、平均をあまり意識する必要はありません。「健康」や「綺麗」の基準はあいまいなため、ひとまず平均という言葉を用いました。
同世代より健康で部屋も綺麗なら、無理に断捨離をする必要はないでしょう。しかし、そうでないなら「した方がいい」といえます。
「今までこれで良かったのだから大丈夫」というのは、いわゆる「老害」の代表的な原因です。こうした「現状維持バイアス」は、年齢が上がるにつれて強まっていく傾向があります。
「今までやらなくてよかったから」という理由で断捨離をしないなら、そもそも「今、良い状態なのか」ということを、冷静に見つめるようにしましょう。
妻がしてはいけない断捨離(捨てるとトラブルになる物)

妻独特のものとしては、やはり「夫の大事なものを捨てる」ということでしょう。もちろん、これは相手が子供でも親でも、勝手にするべきではありません。
「親が家をゴミ屋敷にしている」などの余程の問題がない限りは、相手の物を勝手に捨てないというのは、断捨離の基本です。そして「妻」という立場で考えると、その特に重要な相手の一人は夫となります。
「亭主関白」という意味ではない
これは「亭主関白」のような意味ではありません。法律的に親や兄弟など「生まれつき決まっていた家族」より、夫や妻など「自分で作った家族」が重要なのです。
前者に対しての責任はほとんどないのですが、後者に対しては、男女のどちらも重い責任を負います。もちろん配偶者だけでなく、二人で作った子供についても同様です。
このように法律的には「妻にとって一番大事な人間は、夫と子供」なのです。そのため、断捨離でも「妻がしてはいけない断捨離」といえば、主に「夫の物」に関わるといえます。
(子どもの物も勝手に捨てるべきではありませんが、子どもの場合、深刻なトラブルになることは少ないでしょう)
夫の大事なもので、捨てられがちな物
多くの家庭の奥さんの体験談を集めると、主に下のようなものが「勝手に捨てて喧嘩になるもの」といえます。
- 置いてあるだけで、夫自身も全然使っていない物
- 夫の思い出の品だが、汚くて臭い物
- 物自体は普通だが「その中に何か入っている」物
以下、それぞれのパターンについて説明していきます。
置いてあるだけで、夫自身も全然使っていない物

これは多くの家庭で見られるパターンです。夫や男性に限らず、妻・女性でもよくあることですが「買ったものの、全く使っていない」という物が、多くの家庭で放置されています。
他人から見れば明らかに「捨てるか、売るか」するべき―。しかし、本人は「高いお金を出して買ったから、もったいなくて捨てられない」というパターンです。心当たりがある方も多いのではないでしょうか。
【参考】コトバンク「サンクコスト」
こうした不要物を捨ててはいけない理由
相手が夫であろうと、親などのその他の家族であろうと、こうした不要物を捨ててはいけない理由があります。それは「相手の決断力のなさを批判することになる」ということです。
つまり、相手は「物を捨てられたから怒る」のではないのです。それもあるのですが、一番ショックなのは、自分の決断力のなさを批判されたと感じることにあります。
実際、口に出して批判はしなくても、行動自体で批判したのと同じです。特に男性はプライドが高いため、こうした出来事一つで、夫婦の間に大きな溝ができてしまうことがあります。
このため、たとえ「全然使われていない」ものでも、捨ててはいけないのです。
夫の思い出の品だが、汚くて臭い物

本人にとっては思い出の品だけど、汚くて臭い―、という物もあるかもしれません。たとえば「学生時代に奮発して買った洋書」などです。
図書館に行くと独特の臭いを感じる人が多いでしょうが、実は本にもカビが生えます。特に分厚い百科事典のような書籍は、分厚い分風通しも悪いため、独特の臭いを発しやすいものです。臭いの原因となる紙自体が多いことも、臭う原因になります。
そして、男性がコレクションしたくなるような本に限って、分厚く古いことが多いもの。また、本人にとっては「自分の知性を示すアイテム」なので、居間などの家族の共有スペースに飾ろうとすることが多くあります。
女性も「自分を誇示するアイテム」を、家族のスペースに飾ろうとすることはあります。しかし「それが臭い」ということは、あまりありません。この違いがどこから来るのか説明します。
男性の嗅覚は女性より鈍感
男性(夫)も、臭い・汚いという自覚があれば、わざわざ家族の共有スペースに持ち込んできたりはしません。しかし、男性は嗅覚が女性よりも鈍いのです。
この理由には諸説がありますが、理由の一つは「料理をする時間が短い」ということにあるでしょう。何かを日常的にやるかやらないかの違いは大きく、それが数十年積み重なって、50代の男性・女性の嗅覚の差になるのだといえます。
理由はどうあれ、夫の方が妻より嗅覚が鈍い以上、本人は「臭いと思っていない」ということがあります。そのため、妻が「こんなに臭いものは捨てても誰も文句など言わない」と思っても、夫はそう思っていない可能性が高いのです。

このような物はどうすればいいのか
最終的には時間をかけて話し合うしかありません。しかし、ある程度即効性のある方法としては「人が頻繁に家に来るようにする」手があります。
よほど老化した人でなければ、50代の男性で「来客に汚い部屋を見せて平気」という人はいません。そして、夫が居間などに進出させている私物について、多少なりとも「人から見たら汚いかもしれない」という自覚があれば、自然と片付けるようになるでしょう。
「その自覚がない」場合は難しいのですが、自覚させる方法もあります。たとえば子供の家庭教師などで若い女性に出入りしてもらうのも一つの手です。「若い女の子から見たら、これはちょっと汚いと思うよ」という一言には、それなりの効果があるでしょう。
ただ、こうしたテクニックはあくまで「小手先」のものであり、最終的にはやはり「夫婦間の話し合いを焦らずにする」ことが基本だといえます。
物自体は普通だが「その中に何か入っている」物

これも家族の物を捨てるときに、非常によくあることです。「明らかに捨てていい」と思ったものを捨てても、実は「その中に何かが入っていた」ということが、稀にあります。
「たまたま入っていた」こともあれば、へそくりのように「意識して入れていた」ということもあるでしょう。どちらにしても、大事な物を失ってしまうため、相手はかなり怒ることになります。
これを防ぐにはどうしたらいいか
やはり「勝手に捨てない」ことが基本となります。他のケースと違い、このケースは「明らかに捨てていい物」でも起こりうるトラブルだからです。
妻の断捨離でやってはいけないことを一言でまとめると、「夫に無断で物を捨てる」という一言に尽きます。勝手に捨てない限りは、基本的に大きな問題は起きないでしょう。
主婦がやってはいけない断捨離とは?

50代がやってはいけない断捨離の中でも、特に「主婦がするべきでない断捨離」がいくつかあります。ここではそれらのパターンを3つ紹介します。
理想の生活を過度に追求する
一般的に、男性よりも女性の方が「理想の部屋」の実現を目指すものです。男性も「秘密基地」のような感覚で目指すことはありますが、女性と違い「何かのマニアの部屋」になることが多いといえます。
実際に、インテリアコーディネーターの約75%が女性ということを見ても、これは客観的な数字で説明できることでしょう。そのように女性の方が「インテリアにこだわる」のですが、これが過度の断捨離につながることがあります。
モデルルームのような部屋は、逆にストレスが溜まることも
断捨離を完璧に実行しようとする主婦の方は、モデルルームのような部屋を理想としています。確かにあのような部屋で毎日生活できたら快適でしょう。
ただし、それは「自動的にそうなるなら」です。実際には、自動的にはなりません。芸術家が物を作れば廃材が出るように、人間が生活をすれば何かと「生活感のあるもの」が出てきてしまうのです。
そのような物を、たとえば「服を脱ぎっぱなしにしない!」「この書類は要るの?もう要らないなら捨てて!」などと完璧に捨てようとすると、家の中がギスギスしてしまいます。
仏教にも「掃除地獄」という修行がある

実は、上の例のように「理想の部屋を目指そうとする」という考えは、必ずしも悪いものではないのです。仏教でも「三大地獄行」という修行があり、そのうちの一つに「掃除地獄」があります。
侍真は十二年もの間、浄土院の中から出ずに午前三時に起床して、読経・献膳・五体投地・仏教研究・境内掃除を続けます。
広い庭にほこりひとつ残さず、一切の殺生を禁じ、食事は献膳のおさがりの「一汁一菜」です。
比叡山三大地獄行(回峰地獄・掃除地獄・看経地獄)|東大寺公式サイト
お寺の境内の広さを想像すれば、あの中で「ほこり一つ落とさない」ということが、どれだけ大変かわかるでしょう。ルールはお寺や宗派によって違いますが「落ち葉もNG」というルールもあります。
落ち葉など、季節によっては「常時落ちてくるもの」です。それもすぐに見つけて、すぐに除去しなければいけないのです。
何のためにそんなことをするのか
実は、これにも明確な答えはありません。実際、歴代の仏教者の中でも、一休宗純(一休さん)のように、とんでもなく無頼な生活を堂々としていた人物もいます。また、老荘思想(道教)では「落ち葉など自然なままにしておけ」といいます(無為自然)。
このように、宗教家の中でもまったく違う価値観が衝突しているわけです。このため、最終的にはこうした努力は「ただの好み」といえます。
確かなことは「モデルルームのような部屋を目指す断捨離」と、「掃除地獄」はよく似ているということ。つまり、決して間違った考えではないのです。
間違ってはいないが「苦行」である
このように「完璧な断捨離を目指す気持ち」自体は、修行僧と同じで、悪いものではありません。しかし、修行僧と同じということは、要するに「苦行である」ということ。僧侶たちも自ら「三大地獄行」とまで呼んでいるわけですから、普通は「辛くなる」のです。
「それでもやる」という理由が何かあれば、もちろんそれでいいでしょう。しかし、それで家庭がギスギスするようであれば「そもそも家庭を持つべきではなかった」という結論になるかもしれません。
実際、ブッダも家族を捨てて修行の道に入りました。断捨離でも何でも、理想を追い求めると「人と衝突することが多くなる」というのは意識しておくべきでしょう。
(余談ですが、タモリさんの名言の一つに「やる気がある者は去れ」という言葉があります。これは「真面目な人間は物事の中心しか見えなくなるから良くない」という意味です。理想を追って人と衝突することも、それに似ているといえるでしょう。

経済力がない状態で、使える物を捨ててしまう

これは賛否両論があるでしょうが、50代の主婦の方々のブログで、よく指摘されていることです。簡単にまとめると、下のような主張となります。
- 確かに、バンバン捨てられたらそれがいい
- しかし、いつか必要になるかもしれない
- 捨ててしまうと、その時に「また買わないと」いけない
- そのお金がないなら、捨てるべきではない
要は「お金があるか、ないか」です。
- お金がある…捨てていい
- お金がない…捨てるべきではない
このような考え方ですね。当たり前といえば当たり前かもしれませんが、要は、断捨離はお金持ちの趣味だから、庶民は真似するなという発想ともいえます。
本当に「庶民はすべきではない」のか?
ここがもっとも賛否の分かれるところで、むしろ「物を捨てずに溜め込むからこそ、仕事ができない人間になってお金がなくなる」という指摘も多くあります。実際、仕事ができる人は「お金がない頃から決断が早かった」ことが多いので、これは一理も二理もあるでしょう。
最終的には「自己評価の問題」といえます。「私は(うちは)もっと稼げる」という自信があれば、自然と「バンバン捨てる」という選択肢になるでしょう。逆に、そのような自信がなければどうしても「捨てることに恐怖を感じてしまう」かと思います。
ストレスが溜まらない程度に上を目指すべき
このあたりは完全に個人の価値観の違いになります。しかし「うちはもうこれ以上稼げない」「二度と新しい物は買えないから、今ある物は絶対捨てない」という考えは、心から喜んで言えることではないのではないかと思います。
「本当にそうなんだから仕方がない」と思うかもしれませんが、むしろ「そう思っているからそうなる」という可能性もあります。ストレスが溜まらない範囲であれば、誰でも「今より状況が良くなるなら、その方が良い不動産と思うでしょう。
アランの『幸福論』は「人間はむしろ労苦を喜ぶものだ」と主張していますが、実際「ストレスが溜まらないレベル」であれば、生活を改善する努力は楽しいものです。「嘘だ」と思うなら「自分より自堕落な生活をしている人」を想像してみればわかるでしょう。
おそらくほとんどの人が、
- 「そんな生活は抜け出す方が幸せに決っている」
- 「そのために必要な努力だって、大したものじゃない」
と思うでしょう。同じように「もう稼げないから物は捨てない」という考え方も「抜け出す方が幸せに決っている」可能性があります。
完全に抜け出す必要はありませんが、無理なくできる範囲の努力をして「できるだけスッキリした生活」をできるようにした方がいいでしょう。
「子供の物は勝手に捨てていい」と考える

これは主婦というよりも「母親がやってはいけない断捨離」です。親はしばしば「子供の物は自分が買ってあげたものだから、何をしてもいい」と考えがちです。
たとえば世界的なバイオリニストの高嶋ちさ子さんは、お子さんのゲーム機を破壊したことをツイートし、それが炎上騒動になったことがあります。高嶋さんの場合、お子さんとの関係も良好なようなので問題ありませんが、このような家庭は少なくないでしょう。
子供時代のショックは長く引きずられる
ゲーム機でもおもちゃでも、大人にとっては「たかが」というものです。値段にしたらそれこそ「小銭で買える」「カードに付いていたポイントで買える」というようなものでしょう。
しかし、子供にとってはそうではありません。特に人形やぬいぐるみは、感受性が豊かな子供にとっては「友達」ということも多いものです。
これを実感できる歌のひとつが「クマのぬいぐるみ」です。「みんなのうた」で1987年~2017年まで6期に渡って放送されたので、覚えている人もいるでしょう。下の動画の歌です。
別にこの歌でなくても良いのですが、感情が死んだ人でなければ、何かしらこのような子供時代の思い出があるでしょう。お子さんもそのような思い入れを持って、人形やおもちゃを大切にしているかもしれません。
それを「勝手に捨てる」というのは、子供にとっては軽度の虐待にも映るものです。大人になって「虐待だった」と騒ぎ立てることはなくても、親に対する介護などがおざなりになる、ということは十分に考えられるでしょう。
子供への教育の結果は、いい意味でも悪い意味でも「後からじわじわ来る」ものです。断捨離も大切ですが、子供を持った以上は、一番重要なことは子供という一人の人間を健全に育てることといえます。
断捨離がそのために必要ならするべきですが、そうでないなら「まずは子供の情緒をよく考える」ようにしましょう。
ちなみに「クマのぬいぐるみ」にピンと来た人なら「赤いやねの家」にもピンと来るでしょう。この歌については「実家の片付け・売却」の記事の、こちらの段落でお話ししています。

50代でシンプルライフを送るために整理すべき場所
「終活というわけではないけど、断捨離をしてシンプルライフを送りたい」と思っている50代の方も多いでしょう。ここでは、そのように考えたとき、具体的にどのような場所をどのように、整理していくべきかを説明します。
キッチン…吊戸棚にある物は捨ててかまわない

キッチンで断捨離をするコツは「吊り戸棚にある物は捨てていい」と考えることです。吊り戸棚とは「天井まである高い棚」です。
「いや、大事なものが入っている」と思うかもしれません。しかし、最後に使ったのはいつでしょうか。「3年ほど使っていない」というものは、かなりあるはずです。
本当に必要な物は、吊り戸棚には入れない
これは料理をしている主婦の方なら実感しているでしょうが、本当に必要な物を吊戸棚に入れることはありません。不便で仕方ないためです。
キッチンでも「必要なものは足元にある」のです。もしくは、手元の引き出しにあります。「吊り戸棚にあるものは、原則すべて捨ててかまわない」と考えると、台所の断捨離をしやすくなります。
和室…来客用布団は捨ててレンタルにする

和室の断捨離では「来客用布団を捨てる」のが、特に効果的な断捨離です。まず「来客用」という時点で「ほとんどの日は要らない」ことが確定しています。
布団は意外にかさばるものです。そして、ダニの温床にもなります。
- 押入れの中にダニがいる
- 押入れを開けるのが本能的におっくうになる
- 和室の大掃除をしにくくなる
- 和室が汚くなる
このような流れで、「たかが来客用布団」でも、和室を綺麗にできない原因になるのです。
現代なら貸し布団のサービスが充実している
昔だったら、確かに来客用の布団は必要だったでしょう。しかし、現代は貸し布団というレンタルのサービスが充実しています。
「人が使った布団なんて」と思うかもしれませんが、よく考えてください。ホテルの布団は、たとえスイートルームでも「他人が使った布団」です。
それを考えれば、来客用は「レンタルで当たり前」といえます。むしろ、プロが管理していた分衛生的といえるでしょう。
「ずっと押入れにしまわれていて、ダニが生息している布団の方が非衛生的」ともいえます。このような理由から、お客さんのためにも「来客用布団は捨てる方がいい」という考え方もあるのです。
風呂場…物が少ないので判断しやすい

断捨離が苦手な人が、最初に取り組むといい場所は風呂場です。理由は、他の場所と違い「そもそも物が少ない」ためです。
物が少なければ、問題数の少ないテストのようなもので、簡単に完了します。それが自信となり、断捨離のモチベーションも能力も、徐々に上がっていくでしょう。
終活・断捨離を含めた生前整理はプロにご相談を!

ここまで述べたような終活や断捨離も含めて、生前整理をする場合はプロに相談していただくのがいいでしょう。お一人でできることも多くありますが、相続などの法律・税金が関わることになると、プロに相談するのが一番です。
もちろん「お金もかかるし、全部自分でやりたい」ということもあるかと思います。その場合は、下の記事を参考に生前整理を勧めていただけたらと思います。

まとめ

50代で終活を始めるのは、お子さんにとっても大変良いことです。そして、断捨離は20代や30代の方も取り組んでいるように「終活に関係なく、メリットが大きい」といえます。
実際に終活の断捨離に取り組み始めると、50代では下のような問題を感じることもあるでしょう。
- 体力的に力仕事が難しい
- 相続のことも考えないといけないが、法律や税金のことがよくわからない
- どちらもやろうと思えばできるが、仕事が忙しくて時間がない
このようなときは、ぜひ弊社のような生前整理のプロにご相談いただければと思います。断捨離の力仕事やハウスクリーニングなどはもちろん、全国800以上の士業ネットワークを活用し、お客様のケースにとってベストな弁護士や司法書士、税理士などを紹介させていただきます。
ご相談やご質問は電話・メールの両方で受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。お見積りも完全無料ですので「とりあえず、どのくらいの費用がかかるのか知りたい」というだけのお問い合わせでも歓迎です。
終活や生前整理は「とりあえず、気軽な気持ちで第一歩を踏み出す」のが一番です。その一歩として、まずは漠然とした状態でかまいませんので、弊社にお気軽にご相談いただけたらと思います。
 遺品整理のみらいプロセスの対応エリア
遺品整理のみらいプロセスの対応エリア
遺品整理みらいプロセス にお任せください
遺品整理みらいプロセスは、埼玉・東京・千葉・神奈川の遺品整理、生前整理なら即日にお伺い出来ます。お急ぎの方、現場にはいけない遠方の方など、是非ご相談下さい。